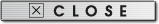生命科学先端研究支援ユニット学術セミナー(第91回~第100回)
| 第97回 | |
| 日 時 | 令和元年5月27日(月)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟Ⅱ7階セミナー室8 |
| 演 題 | 遺伝子改変ゼブラフィッシュを用いた体内時計の光制御に関する研究 |
| 講 師 | 平山 順 先生(公立小松大学保健医療学部・教授) |
| 内 容 |
 体内時計は、生物個体の全身の各細胞に内在する日周性をもつ遺伝子発現のネガティブフィードバックループ(細胞時計)が基本単位です。複数の細胞時計が、外界の光刺激により組織内で同じ時刻に同調する(光同調)と体内時計が構築されます。従って、体内時計の形成機構を理解するためには、細胞時計の日周性形成と光同調の制御機構を解明することが必要です。 これまでの研究は、マウスおよびゼブラフィッシュを用いて、細胞時計の日周性形成における、細胞時計の標的遺伝子プロモーター上のクロマチンリモデリング調節と翻訳後修飾を介した細胞時計構成因子の機能調節の機能を明らかにしています。また、細胞時計の日周性の形成機構は、ヒトを含む哺乳動物とゼブラフィッシュで共通であることを報告しています。 外環境に光同調するために、ヒトといった日中に活動する昼行性生物は細胞時計の時刻を前進させる一方で、マウスといった夜間に活動する夜行性生物は時刻を後退させます。すなわち、細胞時計の光同調の方向が昼行性生物と夜行性生物では逆です。この背景より、細胞時計の光同調の研究は、成果をヒト体内時計の理解につなげるために、昼行性かつヒトと共通の体内時計を有するゼブラフィッシュを用いて進めてきました。先ず、ゼブラフィッシュ胚を用いた解析より、細胞時計の光同調の候補制御因子として、3つの光誘導型の細胞時計構成因子を見出しました。次に、ゲノム編集技術を用いて、これらの光誘導型分子をコードする遺伝子を全て破壊したTriple Knock Out(TKO)ゼブラフィッシュを作出し解析しました。その結果、光誘導型の細胞時計制御分子が、個体内の個々の細胞時計を光同調させ体内時計を形成させることが明らかになりました。さらに、TKO個体を用いた解析により、光誘導性の細胞時計制御分子が、エネルギー代謝を通じて行動量を制御することを示唆する結果を得ました。 本講演では、体内時計の生体の恒常性維持における重要性、ならびに体内時計の形成機構に関するこれまでの研究を紹介します。 |
| 第96回 | |
| 日 時 | 平成30年12月20日(木)午後5時から |
| 場 所 | 共同研究利用棟6階会議室 |
| 演 題 | 放射線リスクコミュニケーション |
| 講 師 | 神田玲子 先生(放射線医学総合研究所・放射線防護情報統合センター長) |
| 内 容 |
 4項目の中で、放射線リスクコミュニケーションについては、平常時の医療現場における必要性に加え、原子力災害医療の視点からの学びの重要性が求められており、各大学での具体化には工夫が必要となります。 そこで、本講演ではリスク認知に関する演習も交えながら、医療者が行なう放射線リスクコミュニケーションにおいて必要とされる放射線リスクの評価や管理に関する知識やコミュニケーションのスキルについて紹介します。 |
| 第95回 | |
| 日 時 | 平成30年7月10日(火)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟Ⅱ7階セミナー室8 |
| 演 題 | がんの先端的放射線治療 |
| 講 師 | 齋藤淳一 先生(本学大学院医学薬学研究部(医学)・教授) |
| 内 容 |
 |
| 第94回 | |
| 日 時 | 平成30年2月9日(金)午後5時から |
| 場 所 | 附属病院2階臨床講義室(1) |
| 演 題 | がんの集学的治療と最新の放射線治療 |
| 講 師 | 櫻井英幸 先生(筑波大学医学医療系・教授) |
| 内 容 |
 本講演では、さまざまながんに対する治療法の変遷をレビューするとともに、最新の放射線治療法に関する研究を紹介する。 |
| 第93回 | |
| 日 時 | 平成30年1月29日(月)午後5時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟2階セミナー室 |
| 演 題 | Biological Effects of Ionizing Radiation: From Non-targeted Response to Precision Medicine |
| 講 師 | Tom K. Hei 先生(米国コロンビア大学メディカルセンター・教授) |
| 内 容 |
 |
| 第92回 | |
| 日 時 | 平成29年11月24日(金)午後5時から |
| 場 所 | 附属病院2階臨床講義室(1) |
| 演 題 | がんに対する放射線治療の現状・課題・私たちの取り組み;低酸素バイオロジーの視点から |
| 講 師 | 原田 浩 先生(京都大学放射線生物研究センター・教授) |
| 内 容 |
 我々は悪性固形腫瘍内部に存在する低酸素領域(腫瘍血管から離れた領域)に着目して、がんが放射線抵抗性を獲得する機序を明らかにし、これを克服する手法を確立することを目指して研究を進めている。Cre-loxPシステムを活用した低酸素がん細胞の細胞系譜実験を通して、低酸素細胞が放射線治療後のがんの再発を担う細胞群であることを証明した。また、遺伝学的なスクリーニング実験を通して、がん細胞の放射線抵抗性を担う遺伝子ネットワークを同定してきた。 本講演では「腫瘍内低酸素領域」と「低酸素誘導性転写因子HIF-1」にフォーカスを当て、「がんが放射線治療抵抗性を獲得する仕組み」と「新たな治療法の確立に向けた私達の取り組み」を紹介する。 |
| 第91回 | |
| 日 時 | 平成28年12月15日(金)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟Ⅱ7階セミナー室7 |
| 演 題 | 疾患モデルマウスを用いた研究:酸化ストレス誘発発がんの抑制に関与する分子機構の解明 |
| 講 師 | 續 輝久 先生(九州大学大学院医学研究院・教授) |
| 内 容 |
 |