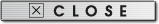生命科学先端研究センター学術セミナー(第41回〜第50回)
| 第50回 | |
| 日 時 | 平成21年11月24日(火)午後6時から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階 ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「PET及びSPECT用インビボ分子イメージング剤の開発研究−脳神経機能の可視化を目指して−」 |
| 講 師 | 柴 和弘 先生(金沢大学学際科学実験センター教授) |
| 内 容 |
 我々は「分子イメージング」研究の中でも、PET・SPECTを利用したインビボ分子イメージング研究、つまり、個体にダメージを与えることなく、生きたまま体内の「分子」の様子を観察し、疾病・疾患での体内変化を鋭敏に捉える放射性核種標識分子プローブの開発研究を行っております。 今回、脳神経機能に関わる「分子」を可視化する分子イメージング研究の中から、アルツハイマー病の客観的早期診断を目的として、アセチルコリン神経系のシナプス小胞トランスポーターであるアセチルコリントランスポーター(AChT)の可視化および合成酵素であるコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)の可視化のためのプローブ開発、また、脊髄小脳変性症の遺伝子治療における遺伝子発現の可視化に関する研究等についてお話し致します。 |
| 第49回 | |
| 日 時 | 平成21年10月21日(水)午後6時から |
| 場 所 | 医薬研究棟4階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「Microbubble Cavitation for Therapy: Present Status and Future Directions」 |
| 講 師 | Paul A. Campbell 先生(英国Dundee大学教授) |
| 内 容 |
Microbubble contrast agents were originally developed to enhance echogenicity in diagnostic sonography. However, their somewhat unique acoustic response and facility to transduct energy into spatially focussed regimes, together with the clinical demand for non-invasive adjuncts and options to conventional therapy, have seen interest in exploring the therapeutic potential of microbubbbles grow steadily within this past decade or more. For the purposes of the present paper, the author has sought to select several key aspects of acoustically driven microbubble interactions, (both with other bubbles, and with cells also) and to assess what we have learned, and perhaps more importantly, what we still require to understand better. This is presented in the context of both in vitro sonoporation experimentation, and also with more clinically related areas such as transdermal drug delivery. En route, we will highlight some personal preferences with in-vitro experiments, namely the advantages to be gleaned by controlling the spatial placement of microbubbles within bespoke optical traps. The objective here is to improve our understanding of their statistical behaviour of interactions, and to validate computational models for eventual optimisation. Observations first centre on individual microbubbles of commercial [low-index] ultrasound contrast agents and their interactions with proximal surfaces. We then progress to the situation of multiple microbubbles in controlled geometries. Some nuances of high speed imaging cameras are highlighted. We also compare our own observations with a selection of corroborative highlights from the literature, and finally, make some suggestions as to where future research efforts might be most fruitfully directed. |
| 第48回 | |
| 日 時 | 平成21年9月1日(火)午後6時30分から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「核内受容体とクロマチン転写」 |
| 講 師 | 加藤茂明 先生(東京大学分子細胞生物学研究所教授) |
| 内 容 |
 本講演では、これら核内受容体と他の細胞内シグナルとのクロストーク機構について、受容体たんぱくの染色体構造調節(Cell, 113, 905, 2003)、タンパク分解制御(Nature, 446, 562, 2007)とヒストン修飾(Nature Cell Biol., 9, 1273, 2007)、DNAメチル化脱メチル化制御による例を紹介することで、核内受容体による新たな遺伝子発現制御の分子機構について触れたい。 |
| 第47回 | |
| 日 時 | 平成21年6月26日(金)午後5時から |
| 場 所 | 附属病院2階臨床講義室(1) |
| 演 題 | 「放射線の人体影響と生体の防護機構」 |
| 講 師 | 神谷研二 先生(広島大学原爆放射線医科学研究所所長) |
| 内 容 |
 本講演では、放射線の人体影響の概要を説明し、ゲノム損傷応答機構と発がんの防御について概説致します。 |
| 第46回 | |
| 日 時 | 平成21年3月2日(月)午後5時から(予定) |
| 場 所 | 附属病院臨床講義室(1) |
| テーマ | 「基本指針における動物実験の自主管理とは」 |
| 演 題 | 「東京大学における動物実験への対応と現状」 |
| 講 師 | 三浦竜一 先生(東京大学ライフサイエンス研究倫理支援室) |
| 内 容 |
近年社会的な意識の高まりを受けて、「安全」、「環境」、「倫理」、「コンプライアンス(法令遵守)」、「アカウンタビリティ(説明責任)」をキーワードとする視点から、社会全体が、教育研究を含めた社会活動全般に対して、適正な実施を強く要請するようになった。国はこの現状に対処すべく法令の制定や改正を行ってきている。こうした流れは、教育研究の分野においては、近年特にライフサイエンス研究を対象としたものが多い。その一つとして、動物愛護法が平成18年6月に改正され、同時に大学を含めた研究機関を対象とする動物実験基本指針が制定された。その中で、研究者が適正な動物実験を実施するように、研究機関に対して教育訓練、自己点検評価、情報公開及び外部評価の実施を課すこととなった。 加えて、基本指針が主に科学的観点と動物愛護の観点からの適正化を定めてあるのに対して、全ての教育や研究で共通する安全確保や環境保全の観点からの適正化にも配慮しなければならない。事故等による健康被害、生態系の破壊・汚染等の発生を防止する必要がある。またカルタヘナ法、外来生物規制法、改正感染症法、麻薬向精神薬取締法等の法令遵守も欠かすことはできない。 ここであげた様々な課題は、全ての研究機関に共通する課題である。上述した社会状況を考慮すると、新たな規則や規制により更に課題が追加されることはあっても、緩和や撤廃は現状期待できそうにない。よって、研究機関はこうした現状といかにうまくつきあっていくかが求められ、研究機関の実情に応じた対応が必要とされる。今回、こうした課題に対する本学の総合的な取り組みをご紹介する。 |
| 演 題 | 「AAALAC Internationalの認証と動物実験施設」 |
| 講 師 | 黒澤 努 先生(大阪大学大学院医学系研究科) |
| 内 容 |
2005年に我が国の動物愛護法の改定に際して日本学術会議は動物実験の過剰な法的規制を懸念し、研究者による自主的な動物実験管理を提言した。とくにその中で動物実験の第3者評価の体制整備を提案した。これを受け、各界で第3者評価システムの構築が行われているが、研究者による自主的な動物実験管理では米国に発祥し約50年の歴史を持つAAALAC International(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care and Use:国際実験動物愛護評価認証協会)が国際的な団体として存在する。AAALAC Internationalは研究機関内で策定された動物実験プログラムを評価認証するとしていて、適切であれば認証する団体である。 現在、全世界30カ国の760以上の研究機関が認証されているが、公的な機関、著名な大学、製薬企業、民間研究所など幅広く認証している。AAALAC Internationalの権威は極めて高く、米国ではその認証がなければ動物実験を含む研究計画に対して公的な研究費が申請できないほどである。1996年に欧州の研究機関の要請により名称を変更しただけでなく、欧州に支部を設立し、本格的な国際団体となった。現在北米3Sectionsと欧州1Sectionに分かれたCouncil会議により研究機関訪問と認証がおこなわれている。 アジア地区では韓国が率先してこの認証を求め、やがて中国でもその重要性が認識され、アジア全体で40以上の研究機関が認証を受けるに至っている。我が国ではこれまでAAALAC Internationalの認証の重要性は重視されていなかったが、日本学術会議の提言以降にわかに関心が高まり、多くの研究機関が関心を寄せている。このためアジア地区を含む環太平洋地区の活動を独立させることとなった。すでにアジア地区からは8名のCouncilsと多数のAdHoc consultantsが任命されているが、このCouncilsによるSectionを新たに構成し、欧州と同等の地位を与えることを決定した。これにより施設訪問は現地のCouncilが担当することとなり、多大な旅費が不要となったことにともない、申請料が実質的な値下げとなった。 まず東南アジア地区に兼任のDirectorを任命した。しかし、わが国にはわずか2名のCouncilと2名のAdHoc consultantsが存在するのみであり、我が国からも、もっと多くのAAALAC Internationalの活動に参加する専門家の登場が期待される。 我が国では民間企業が当初申請に意欲的で、認定第一号となったのも民間企業の研究施設であった。しかし、この動きはやがて製薬企業にも広がり、中外製薬、萬有製薬そして、アステラス製薬が認証を受けた。さらにこの国際認証は大学にも広がり、北海道大学は我が国の大学として初めて完全認証を取得している。仄聞するところではすでにいくつかの大学も認証申請の準備を開始しているとのことである。 |
| 第45回 | |
| 日 時 | 平成20年11月27日(木)午後5時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟6階会議室 |
| 演 題 | 「新薬の開発研究におけるイノベーション」 |
| 講 師 | 榑林陽一 先生(神戸大学連携創造本部教授) |
| 内 容 |
 本講演では、最新の創薬研究のプロセスとその特徴、そして創薬力の低下をもたらしていると考えられる諸因子について概説する。また、創薬力の低下を改善するために生み出されてきたイノベーションの数々を紹介し、この4半世紀、創薬科学の領域でイノベーション創出の旗手を務めてきた米国バイオベンチャー企業の発展の歴史と、ライフサイエンス産業の将来展望についても解説する。 |
| 第44回 | |
| 日 時 | 平成20年10月24日(金)午後5時から |
| 場 所 | 講義実習棟1階101講義室 |
| 演 題 | 「多能性を規定する転写因子ネットワークの構造」 |
| 講 師 | 丹羽仁史 先生(理化学研究所発生・再生科学総合研究センター) |
| 内 容 |
分化多能性(pluripotency)は、最も厳密には、個体を構成する全ての種類の分化細胞に分化出来る能力を指す。このような能力を持つ細胞としては、胚盤胞の内部細胞塊やそれに由来する胚性幹細胞(ES細胞)があるが、今日では転写因子の強制発現により、分化細胞からも誘導することが可能となっている。この発見は、多能性が細胞の分化形質の一つとして、転写因子ネットワークにより規定されていることを如実に物語っているが、ではこの多能性を規定する転写因子ネットワークの構造はどのようなものなのだろうか?多能性維持に必須な転写因子であるOct3/4やSox2は、Nanogとともにポジティブ・フィードバック制御を構成し、自らの発現を維持していることが示唆されているが、多能性幹細胞がシグナルに応答して分化を実行するためには、この安定状態を破綻させる機構も必要となる。Klf4は、多能性を誘導する上で必須であるが、そのES細胞における機能は、解析が進んでいない。我々は最近、Klf4が?Oct3/4,Sox2と協調して標的遺伝子転写活性化に寄与すること、?強制発現によりマウスES細胞のLIF非依存的自己複製を維持できること、?LIF-STAT3の直接の標的遺伝子であること、を見出した。一方で、胚性癌細胞P19では、Klf4は発現していないにもかかわらず、Oct3/4とSox2の発現は維持されている。これらの知見を総合的に解釈すると、多能性を維持する転写因子ネットワークは、シグナルを統合して伝達するネットワーク(Klf4, Nanog etc)とこれらを受けて多能性を直接規定するネットワーク(Oct3/4, Sox2 etc)に分類出来ると考えられる。 本講演では、この「転写因子ネットワーク階層モデル」について概説し皆様のご批評を乞いたい。 |
| 第43回 | |
| 日 時 | 平成20年9月10日(水)午後5時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟6階会議室 |
| 演 題 | 「海馬シナプス可塑性に関係するプロテアーゼ」 |
| 講 師 | 塩坂貞夫 先生(奈良先端科学技術大学院大学教授) |
| 内 容 |
 私どもは1995年にマウス海馬よりシナプス間隙に存在する新規の分泌型プロテアーゼ・ニューロプシンをクローニングいたしました。この10年の間に私どもはニューロプシンが海馬・大脳皮質の、学習のモデルである長期増強を制御し、とくにワーキングメモリーと関連していることを明らかとしてきました。このニューロプシンは単シナプスだけでなく、時間的にも空間的にも離れた別のシナプス間の後期連関可塑性に関与し、この連関にはニューロプシンがインテグリン、L型カルシウムチャンネルなどを修飾することによってシナプスタグの形成に関わります。 本セミナーでは、現在開発中の自由行動下でプロテアーゼの活性変化をイメージングする方法についても触れて、ご批判を仰ぎたいと思います。 |
| 第42回 | |
| 日 時 | 平成20年7月22日(金)午後5時から |
| 場 所 | 医学部研究棟4階104講義室 |
| 演 題 | 「色素性乾皮症および関連DNA修復欠損遺伝病患者における発がん感受性と神経障害の機構解析」 |
| 講 師 | 森 俊雄 先生(奈良県立医科大学) |
| 内 容 |
遺伝情報を担うゲノムDNAは、生命が正常に営まれるためには安定に維持されなければならないが、実際は内的および外的要因により日常的に傷つけられている。ヒトにおける最大の外的要因は太陽紫外線であり、シクロブタン型ダイマーや(6-4)型ダイマーなどのDNA損傷を誘発し、細胞致死、突然変異、がん化などを引き起こす。ヒト細胞は紫外線DNA損傷に対し様々な反応を示すが、最も重要なものはヌクレオチド除去修復(NER)機構による修復である。事実、NER欠損遺伝疾患である色素性乾皮症患者は太陽露光部に健常人の数千倍の頻度で皮膚がんを発症する。しかし、不思議なことに、別のNER欠損遺伝疾患であるコケイン症候群や硫黄欠乏性毛髪発育異常症(TTD)患者では日光過敏症を示すが皮膚がん発症頻度は上昇しない。 一方、重要なことには、NER欠損遺伝疾患は日光過敏症に加え、進行性の神経障害を発症する。しかし、その機序は未だ不明である。私達は、世界に先駆けて紫外線DNA損傷に対するモノクローナル抗体を作製し、DNA修復実験系の開発およびその応用に取り組んできた。この技術を基に、修復異常疾患における分子病態の解析、特に皮膚がん感受性差を生じる機構、および神経障害発症機構について研究してきたので報告する。 |
| 第41回 | |
| 日 時 | 平成20年7月4日(金)午後5時から |
| 場 所 | 附属病院2階臨床講義室(1) |
| 演 題 | 「造血幹細胞の放射線感受性とサイトカインの作用」 |
| 講 師 | 柏倉幾郎 先生(弘前大学大学院保健学研究科教授) |
| 内 容 |
造血システムは、自己複製能と多分化能を有する少数の多能性造血幹?細胞と、それらを取り巻くストローマ細胞群により構築される特殊な造血微小環境(ニッチ)およびサイトカインと呼ばれる生理活性因子によって形成される複雑なネットワークのもとに制御されている。この過程において、造血幹細胞はリンパ球系と骨髄系に分化し、骨髄系はさらに各種前駆細胞を経て最終的に機能をもつ好中球、赤血球および血小板等の成熟血液細胞へと分化する。これまでの膨大な研究から、造血幹細胞、造血ニッチやサイトカインネットワークなど造血メカニズムの詳細が解明されてきたが、例えば造血幹細胞の放射線感受性やサイトカインの作用に関してなど不明な点も多い。 演者はこれまで、ヒト造血幹細胞から巨核球・血小板に至る放射線感受性とサイトカインの作用について検討し、白血球や赤血球前駆細胞に比べて放射線感受性であることや、TPOと共にインターロイキン−3とのコンビネーションが効果的であることを明らかにしてきた。今回は、ヒト造血幹細胞の放射線感受性とサイトカインの作用のうち、巨核球・血小板造血を中心に得られえたこれまでの成果を紹介すると共に、巨核球・血小板造血を促進する因子の探索や、放射線曝露されたヒト造血幹細胞からの増幅・再生の取り組みを紹介したい。 |