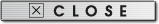生命科学先端研究センター学術セミナー(第21回〜第30回)
| 第30回 | |
| 日 時 | 平成18年11月13日(月)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 |
1:「温熱治療に伴う免疫活性の賦活メカニズム−熱でガン細胞を死滅させることは可能か−」 2:「DNAチップなどによる遺伝子発現情報の処理技術の開発と疾病の発症予測−テーラーメイド医療は可能か−」 |
| 講 師 | 小林 猛 先生(中部大学応用生物学部教授) |
| 内 容 |
 酸化鉄微粒子をリポソームで包み、その表面にガン細胞を認識できるモノクローナル抗体を化学的に結合させる、あるいは陽電荷脂質をリポソームに添加する、ことによって、酸化鉄を腫瘍部位にだけ集積させることができます。交番磁界を照射すると、腫瘍部位だけの加温が可能となり、ガン細胞を死滅させることができます。さらに、加温に伴って大量に生成するヒートショックタンパク質が関与したキラーT細胞の賦活が認められました。この賦活メカニズムなどについて説明します。 演題2 情報科学と生物科学は共に発展著しい分野ですaACその交差点であるバイオインフォマティクスは更に発展著しい分野です。DNAチップなどによる遺伝子発現情報が比較的容易に入手できるようになるaACバイオインフォマティクスの手法を使ってテーラーメイド医療は可能となるかもしれません。しかaAC遺伝子発現情報を市販のソフトだけで処理するaACもどかしく感じるようになります。コストに見合った精度の高い処理技術を開発しなけれaACテーラーメイド医療は掛け声だけに終わってしまいます。これまで悪戦苦闘してきた結果を紹介します。 |
| 第29回 | |
| 日 時 | 平成18年11月10日(金)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟4階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「グリア細胞や神経幹細胞から神経変性疾患を考える:新しい脳ダイナミクスの考え方」 |
| 講 師 | 成田 年 先生(星薬科大学助教授) |
| 内 容 |
 |
| 第28回 | |
| 日 時 | 平成18年10月27日(金)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「生体機能保持細胞株の樹立と創薬科学研究への利用」 |
| 講 師 | 帯刀益夫 先生(東北大学加齢医学研究所教授) |
| 内 容 |
 我々は、温度感受性SV40T-抗原遺伝子導入トランスジェニックマウス、およびラットを作出し、多様な組織から生体の分化機能を保持した不死化細胞株を樹立する方法を確立した。本講演では、不死化遺伝子導入トランスジェニクマウス、ラットからの多様な分化機能保持細胞株の樹立と、その生体機能解析への利用の具体例について紹介する。これら分化機能保持細胞株を用いて培養系で組織機能の再構成を進めてゆけば、将来的には組織再生医学研究へと発展させられる。また、これら細胞株は、薬理学、毒性研究、動物実験代替法への利用、生体機能を反映した医薬品スクリーニング系の開発など、創薬科学の基盤的技術として発展するものと期待される。 |
| 第27回 | |
| 日 時 | 平成18年10月24日(火)午後5時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟5階会議室 |
| 演 題 | 「遺伝子改変マウスが空を飛び交う時代がやってくる!」 |
| 講 師 | 中潟直己 先生(熊本大学生命資源研究・支援センター教授) |
| 内 容 |
 |
| 第26回 | |
| 日 時 | 平成18年10月23日(月)午後4時から |
| 場 所 | 医薬研究棟4階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「6π-電子系電子環状反応の活用による生物活性天然物合成」 |
| 講 師 | 日比野 俐 先生(福山大学薬学部教授) |
| 内 容 |
 1.抗酸化作用および神経細胞保護作用を有する多官能性カルバゾールアルカロイドの合成研究: インドールの2位あるいは3位にアレン中間体を組み込んだ 6π-電子系電子環状反応の開発と展開 2.マイクロ波(MW)照射下でのaza 6π-電子系電子環状反応の活用に関する研究: 1986年からこのMWの合成化学への利用が始まったと言われております。この反応は、反応速度の加速、収率の向上、溶媒中あるいは無溶媒中でも進行、反応系内を均一に加熱することから再現性が高いという点が特徴として挙げられています。Diels-Alder反応やClaisen転位などでの活用は知られていましたが、電子環状反応では全く報告が無かったことから、MW照射下におけるaza 6π-電子系電子環状の活用に関する展開を試みました。 |
| 第25回 | |
| 日 時 | 平成18年10月6日(金)午後4時から |
| 場 所 | 医薬研究棟4階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「酵素のダイナミックな作用機序に基づく新しい創薬研究」 |
| 講 師 | 西村紳一郎 先生(北海道大学大学院先端生命科学研究院教授) |
| 内 容 |
 このたびは高次構造解析が進展している哺乳類のガラクトース転移酵素において観察された基質結合に伴うダイナミックなループ構造変化を特異的に阻害する分子の設計コンセプトについて紹介した後、高次構造が不明のヒトフコース転移酵素やシアル酸転移酵素などの阻害剤探索への応用研究の成果についてお話したい。 |
| 第24回 | |
| 日 時 | 平成18年5月10日(水)午後3時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 司 会 | 鈴木信雄 先生(金沢大学) |
| 演 題 | 「メラトニンの多彩な機能と新たな展開」 |
| 講 師 | 服部淳彦 先生(東京医科歯科大学教養部) |
| 内 容 |
 |
| 演 題 | 「歯と骨とウロコの話:魚鱗の再生過程から見えてくるもの」 |
| 講 師 | 田畑 純 先生(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科) |
| 内 容 |
 そこで、最初にこれまで行ってきた「歯胚の器官培養系」や「エナメル芽細胞の初代細胞培養系」を用いた演者の研究について簡単に紹介し、次に現在取り組んでいる「魚鱗を用いた実験系」を紹介したい。魚鱗はハイドロキシアパタイトを主成分とする硬組織であり、同時に上皮付属器官としての特徴も備えていることから、歯の実験モデルとして好適であると思われる。また、強い再生能を持つこと、構造がシンプルであることなどから、歯にはない利点があり、再生実験や培養実験に向いた材料と位置づけられる。そこで、再生過程における組織学的な変化、細胞たちの振る舞いなどを紹介しながら、歯・骨・ウロコの共通点や相違点、それぞれの持つ面白さなどをお伝えしたいと考えている。 |
| 第23回 | |
| 日 時 | 平成18年4月20日(木)午後5時30分から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「ナショナルバイオリソースプロジェクト 『ニホンザル』の現状とサルを用いた先端的解剖学的研究」 |
| 講 師 | 高田昌彦 先生((財)東京都医学研究機構東京都神経科学総合研究所) |
| 内 容 |
研究用ニホンザルの繁殖と安定供給を目指して2002年度にスタートしたナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザル」もいよいよ5年目を迎え、母群の確保、繁殖・飼育体制の充実、供給の実施と順調に進展している。 本セミナーでは、その現状について簡単に説明するとともに、「サルを用いた先端的解剖学的研究」と題して、狂犬病ウイルスや様々なウイルスベクター(アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス、レンチウイルス)を用いたサルの脳研究に関する最新の知見を紹介したい。 |
| 第22回 | |
| 日 時 | 平成18年2月20日(月)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「消化管腫瘍発生によるWntとPGE2」 |
| 講 師 | 大島正伸 先生(金沢大学がん研究所教授) |
| 内 容 |
 |
| 第21回 | |
| 日 時 | 平成18年1月27日(金)午後4時から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「触媒的環化アルケニル反応の開発と天然物合成への展開」 |
| 講 師 | 豊田真弘 先生(大阪府立大学大学院理学系研究科教授) |
| 内 容 |
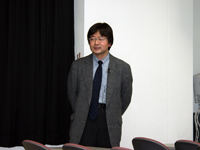 講演では、著者らが触媒的環化アルケニル化反応を開発するまでの経緯と、天然物合成への展開について紹介する。 |