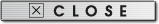生命科学先端研究センター学術セミナー(第11回〜第20回)
| 第20回 | |
| 日 時 | 平成18年1月20日(金)午後5時30分から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「ストレス防衛反応の表出と基礎血圧の決定におけるオレキシンの役割」 |
| 講 師 | 桑木友之 先生(千葉大学大学院医学研究院教授) |
| 内 容 |
 |
| 第19回 | |
| 日 時 | 平成17年12月16日(金)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| テーマ | 「マイクロバブルとナノパーティクルの医学生物学への利用」 |
| 演 題 | 「パルス超音波照射下での細胞膜損傷と修復のメカニズム: 気泡のふるまいの超高速画像解析」 |
| 講 師 | 工藤信樹 先生(北海道大学大学院情報科学研究科教授) |
| 内 容 |
 |
| 演 題 | 「光触媒ナノ粒子と超音波化学のカップリング:殺菌技術・がん治療への応用」 |
| 講 師 | 清水 宣明 先生(金沢大学自然計測応用研究センター教授) |
| 内 容 |
 |
| 第18回 | |
| 日 時 | 平成17年12月12日(月)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「アルツハイマー病感受性遺伝子の探索」 |
| 講 師 | 桑野良三 先生(新潟大学脳研究所附属生命科学リソース研究センター) |
| 内 容 |
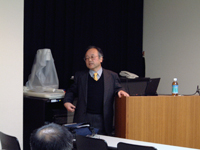 本セミナーでは、我々が推進しているアルツハイマー病の遺伝的危険因子探索について紹介したい。 |
| 第17回 | |
| 日 時 | 平成17年9月21日(水)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「ヒトの骨に代わる魚類のウロコを用いた測定系の開発と医療への応用」 |
| 講 師 | 鈴木信雄 先生(金沢大学自然計測応用研究センター臨海実験施設) |
| 内 容 |
魚のウロコには、骨を作る細胞(骨芽細胞)と骨を壊す細胞(破骨細胞)とが共存している。そのことに注目し、骨に代わる新しい測定系を開発した。この方法により、以前まで培養が困難だった破骨細胞の培養が容易に行える。骨芽細胞と破骨細胞の共存培養を行うので、骨に対するホルモン等の生理活性物質の作用を正しく評価できる。さらに、ウロコにはコラーゲン等の骨基質タンパク質も共存し、骨を薄く輪切りにしたような構造をしているので、重力や磁場に対する刺激にも非常に敏感に反応する、という利点が挙げられる。また最近、超音波によるメカニカルストレスにも応答し、骨芽細胞の活性を上昇することもわかった。 一方、魚のウロコは再生することから、この現象を利用して、ウロコの骨再生を観察した。その結果、頭蓋骨の形成過程と非常によく似ており、骨形成のモデルとしても使用可能であることが判明した。さらにメダカでは、ウロコの欠損系統が発見され、その原因遺伝子は歯及び毛の形成に必須な遺伝子であることが報告されている。したがって、ウロコの研究が歯や毛髪の研究にも貢献できる可能性が高い。 |
| 演 題 | 「血小板由来増殖因子(PDGF)研究の変遷と展望」 |
| 講 師 | 笹原正清 先生(本学医学部教授) |
| 内 容 |
血小板由来増殖因子(PDGF)は間葉系細胞に対する主たる増殖因子の一つである。生体における細胞の増殖・分化に端を発した研究は、さらに、様々な細胞の機能制御における役割にまで展開している。 今回のセミナーでは、これらの世界の研究の流れにおける我々のPDGFについての研究の変遷を紹介し、今後の研究の展望を述べてみたい。 |
| 第16回 | |
| 日 時 | 平成17年8月9日(火)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「Magnetic Resonance Imaging Studies of Tumor Physiology」 (腫瘍生理学における磁気共鳴イメージング) |
| 講 師 |
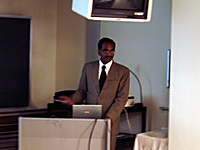 |
| 第15回 | |
| 日 時 | 平成17年7月11日(月)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 |
1) Effects of impulse low dose X-ray irradiation on tumor and normal cells.
2) Inhibitory effects of water soluble bioantioxidants on the chemical and radiation-nduced damage in mice. |
| 講 師 |
 |
| 第14回 | |
| 日 時 | 平成17年1月27日(木)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「ストレスによるPKB(Proein Kinase B、tAkt)活性化機構の解析」 |
| 講 師 | 松崎秀紀 先生(神戸大学バイオシグナル研究センター) |
| 内 容 |
細胞は増殖因子、ホルモンなどの生理活性物質、ストレスなどの多様な刺激に応じてその機能を調節しており、刺激の受容から応答に至る細胞内シグナル伝 達経路ではタンパク質リン酸化酵素が重要な役割を担っている。Protein KinaseB(略称PKB、別名Akt)は、アミノ末端側にPleckstrin homology(PH)ドメイン、カルボキシル末端側にリン酸化触媒ドメインを有するタンパク質リン酸化酵素である。 PKBは細胞増殖因子刺激に伴い、Phosphatidylinositol (PI)3-kinaseの下流標的因子として活性化され、増殖や代謝の調節、アポトーシスの抑制に貢献することが知られている。PKBの活性化機構としては、PKBがPHドメインを介してPI3-kinase反応産物と結合して細胞膜上へとリクルートされ、上流リン酸化酵素PDK1によりリン酸化を受けることが提唱されている。一方、私たちはPKBが細胞増殖因子のみならず過酸化水素刺激や熱ショックなどのストレスによっても活性化されることを報告している。そこで、ストレスによるPKB活性化経路の解析を行ったところ、過酸化水素刺激はPI3-kinaseを活性化して細胞増殖因子と同様にPKBの活性上昇を誘導し、これに対して熱ショックは部分的にはPI3-kinaseを介してPKBを活性化するものの、PI3-kinaseとは独立の経路を介してPKBを活性化することが示された。即ち、熱ショックによるPKB活性化にはPI3-kinase反応産物のPHドメインへの作用、並びにPKBリン酸化反応は必須ではなく、熱ショックは細胞増殖因子とは異なる分子機構によりPKB 活性化を誘導することが明らかになった。 以上の結果から、PKBが細胞増殖因子のシグナル伝達のみならずストレス応答にも関与し、それぞれの細胞刺激に対応した役割を担うことが推定される。 |
| 第13回 | |
| 日 時 | 平成16年11月19日(金)午後6時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「超音波治療技術の研究開発」 |
| 講 師 | 佐々木一昭 先生(日立製作所中央研究所ライフサイエンス研究センター) |
| 内 容 |
強力収束超音波治療(High Intensity Focused Ultrasound、HIFU)は、生体の超音波吸収に起因する発熱原理を治療に応用したもので、現在子宮筋腫や前立腺癌の治療に臨床応用されている。しかしながら、収束超音波の焦点は、幅として1ミリ程度の針のように細長い形状をしており、一回の照射で加熱凝固できる体積は小さい。したがって、大きな腫瘍を治療するためには、焦点を電子的・機械的に走査して、腫瘍全体を満遍なく照射することになり、治療に長時間を要するという問題点が存在する。広く臨床へ普及するためには、治療効率の向上が非常に重要になってきている。そこで、我々のグループでは超音波加熱凝固治療の効率化を検討してきた。 本セミナーでは、収束超音波の焦点領域を拡大することのできるスプリットフォーカス方式や可変 焦点トランスデューサの開発、マイクロバブルを利用した超音波加熱作用増強などについての研究を紹介する。また、時間が許せば、超音波の非熱的作用である音響化学作用を利用した癌治療の基礎的研究結果についても紹介したいと考えている。 |
| 第12回 | |
| 日 時 | 平成16年10月20日(水)午後6時から |
| 場 所 | 医薬研究棟5階放射線基礎医学ゼミナール室 |
| 演 題 | 「生物の雄・雌が決まる仕組みはどこまで解明されたか」 |
| 講 師 | 星 信彦 先生(神戸大学農学部教授) |
| 内 容 |
生物は遺伝的多様性を獲得するため有性生殖という、次世代に遺伝情報を受け継ぐシステムを構築してきた。いうなれば、種の保存のための基盤が「性の決定・分化」であり、生物の雄・雌を決まる仕組みは極めて重要な個体発生の分化過程あるいは生命活動と考えられる。 「性分化」のステップは遺伝的に支配されていると考えるのが一般的であるが、これは哺乳類などの比較的高等な脊椎動物に当てはまることで、すべての動物種の性が遺伝的支配の元に決定されるわけではない。よく知られたことであるが、ある種の爬虫類では孵卵時の温度により性が決まり、また、ある種の魚では集団内の社会的地位や環境要因によって性を変えることができる「性の可塑性」を特徴とするなど下等動物では遺伝的支配によらないメカニズムが普通であり、性分化には動物種間でかなりの多様性が認められる。 本講演では、最新の分子遺伝学的解析データを踏まえ、性の決定・分化機構について概説し、時間が許せばヒトの性分化異常症についても紹介したい。 |
| 第11回 | |
| 日 時 | 平成16年2月12日(木)午後5時から |
| 場 所 | 医薬研究棟3階ゼミナール室(1)(2) |
| 演 題 | 「再生医療と新産業の可能性」 |
| 講 師 | 三宅 淳 先生(独立行政法人産業技術総合研究所ティッシュエンジニアリング研究センター長) |
| 内 容 |
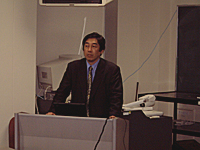 この種の技術を進めるに必要な要素技術は、幹細胞技術、装置・システム開発、ゲノムネットワーク情報を用いた分化誘導技術、ナノバイオテクノロジーであり、それらが相互作用することによって新規な技術領域が拓かれつつある。講演ではこれら重要な要素技術の例を示す。 将来、再生医療をはじめとする先進医療が経済活動の中で果たすべき役割は、第一は健常者の割合を高めることである。病気を根治することにより、質の良い労働力が増加することは、生産力の増大、富の増大に結びつく。第二は先端医学関連の産業と研究開発を活発化することで、他の産業を誘発すると共に、新たな知的価値を創出し、資金の流入と早い回転を可能にする。直接的な価値生産に対する寄与ではなく、経済の活性化とのリンクが重要である。先端医療がこれまでの宇宙開発のように国レベルの重点課題となれば、大きな国家予算が投入され、経済のエンジンがまわることになる。 |