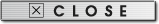生命科学先端研究センター学術セミナー(第61回〜第70回)
| 第70回 | |
| 日 時 | 平成23年6月24日(金)午後5時から |
| 場 所 | 附属病院2階 臨床講義室(1) |
| 演 題 | 「染色体転座形成の分子機構」 |
| 講 師 | 田代 聡 先生(広島大学教授) |
| 内 容 |
 |
| 第69回 | |
| 日 時 | 平成23年3月10日(木)午後3時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟6階会議室 |
| 演 題 | 「How genotoxic stress activates transcription factor NF-κB: A tale of poly (ADP-ribose)- and ubiquitin-scaffolds」 |
| 講 師 | Claus Scheidereit 先生(ドイツ マックス・デルブリュック分子医学研究所所長) |
| 内 容 |
  |
| 第68回 | |
| 日 時 | 平成23年3月7日(月)午後5時から |
| 場 所 | 医薬薬学研究棟3階 セミナー室1 |
| 演 題 | 「放射線によるDNA損傷の修復機構と高発がん性遺伝病」 |
| 講 師 | 田内 広 先生(茨城大学教授) |
| 内 容 |
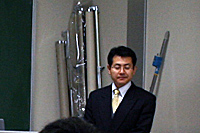 我々は、放射線高感受性や高発がん性を示す遺伝病、ナイミーヘン症候群の責任遺伝子NBS1を中心に、DNA二重鎖切断修復機構の解析を行っており、一連の研究からDNA損傷に対して発がんを防ぐしくみの一端も見えつつある。 このセミナーでは、それらの研究成果を紹介するとともに、がん放射線治療にDNA損傷修復機構を応用するための基礎研究についても触れたい。 |
| 第67回 | |
| 日 時 | 平成22年12月6日(月)午後2時から |
| 場 所 | 共同利用研究棟6階会議室 |
| 演 題 | 「Modification and function of the carboxy-terminal domain of RNA polymerase II (CTD)」 |
| 講 師 | Dirk Eick 先生(ドイツ ヘルムホルツ環境健康センター教授) |
| 内 容 |
 |
| 第66回 | |
| 日 時 | 平成22年12月6日(月)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟II7階 セミナー室8 |
| 演 題 | 「腫瘍血管を標的とした放射線治療効果の増強と分子機構」 (Enhancement of radioresponse in solid tumors by targeting tumor angiogenesis) |
| 講 師 | 三浦雅彦 先生(東京医科歯科大学教授) |
| 内 容 |
 本講義では、我々が開発を進めている硫酸糖脂質の放射線との併用効果とその増感機構について概説する。また、腫瘍の放射線反応性の可視化の一環として我々が進めてるFluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator(Fucci)を用いた研究についても紹介する。 |
| 第65回 | |
| 日 時 | 平成22年11月24日(水)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟II7階 セミナー室8 |
| 演 題 | 「メラトニン研究の基礎と最前線」 |
| 講 師 | 服部淳彦 先生(東京医科歯科大学教授) |
| 内 容 |
メラトニンは本当に不思議な物質である。松果体が「内分泌の墓場」などと呼ばれ、ほとんど見向きもされなかった時代から研究に携わってきた者にとって、今日のような注目のされ方には隔世の感があり驚くばかりである。 ウシの松果体より単離されたメラトニンは、1995年我々が高等植物にも存在することを報告して以来、広く生物界に存在する物質であるという認識が広まった。脊椎動物の松果体より夜間に分泌されるメラトニンは、夜の時刻情報の伝達物質としての作用を持つ。すなわち、「体内時計に対する同調効果」(一般には睡眠促進効果として捕らえられている)に関しては、ヒトではリズム障害者にかぎらず、健常者(小児から老人)に対しても、メラトニンの投与により入眠までの時間の短縮や睡眠の改善が報告されている。一方、生体内のさまざまな器官で産生されるメラトニンに関しては、フリーラジカルのスカベンジャーとしての機能が注目されている。すなわち、ヒドロキシルラジカル(HO・)を始めとするいくつかのフリーラジカルを直接消去、あるいは生体内の抗酸化に関わる酵素(SODなど)を間接的に活性化することにより、フリ−ラジカルから生体を防御しているという報告が数多く出されている。 最近では、メラトニンの骨代謝に関わる新しい機能が明らかにされつつある。これまで、加齢に伴いメラトニンが減少することから、骨粗鬆症との関連が示唆されていたが、我々の研究(2002年)により初めて、メラトニンに破骨細胞に対する抑制効果のあることが明らかとなった。また、様々な新規メラトニン誘導体を合成し作用させたところ、破骨細胞を抑制し、かつ骨芽細胞を活性化させる誘導体を見出した。最近我々は、老齢マウスを用いて、メラトニンに老人性骨粗鬆症の予防効果があること、さらに、マウスやショウジョウバエを用いて加齢性記憶障害(認知症)に対しても予防効果があることを見出している。現在、これらのメカニズムの解明に向かって研究中である。いずれにしても、今後、メラトニンあるいは新規メラトニン誘導体に、骨粗鬆症や認知症に対する予防あるいは治療薬としての新たな展開が期待される。 本講演では、メラトニンについて、基礎から臨床応用に関する新しい研究内容を紹介し、メラトニンという物質について広く知ってもらいたいと考えている。 |
| 第64回 | |
| 日 時 | 平成22年10月29日(金)午後5時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟II7階 セミナー室8 |
| 演 題 | 「DNA損傷修復およびチェックポイント機構におけるp53結合蛋白質1(53BP1)の役割」 |
| 講 師 | 岩淵邦芳 先生(金沢医科大学教授) |
| 内 容 |
 |
| 第63回 | |
| 日 時 | 平成22年10月20日(水)午前10時から |
| 場 所 | 分子・構造解析施設セミナー室(共同利用研究棟2階) |
| 演 題 | 「New Dimension of Mass Spectrometry, From Now and Future. Theory and New Applications. - For The Next Generation of Young Scientists -」 |
| 講 師 | 板垣又丕 先生(米国コロンビア大学) |
| 内 容 |
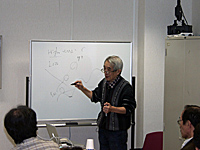 富山大学でもImaging Mass Spectrometryに関するセミナーが開催されており、日本の質量分析研究水準、関心も世界的に遜色がありません。しかし、実情は、大学教育の中心から少し外れた所にあって、アメリカも同じですが、個人個人の興味、自己学習によって支えられているような気がします。 NMR測定は試料を試料管に入れれば、ほぼ均質の結果が得られますが、MSは測定法によって異なる姿を示します。もう少しこの世界の真実を知れば、面白いと思いませんか。Mass Spectrometryの世界、面白さを理解してもらえるよう、時間軸とエネルギー軸の視点からMSの全貌を捉える試みを、無謀かもしれませんが、やってみたいと思います。 今持っている皆さんの研究対象試料と重ね合わせて、質疑応答させてもらえれば幸いです。 |
| 第62回 | |
| 日 時 | 平成22年10月1日(金)午後4時から |
| 場 所 | 薬学部研究棟II7階 セミナー室8 |
| 演 題 | 「霊長類実験動物マーモセットへの期待と理化学研究所脳科学総合研究センター新実験動物飼育行動解析棟の紹介」 |
| 講 師 | 高橋英機 先生(理化学研究所 脳科学総合研究センター) |
| 内 容 |
(1)霊長類実験動物マーモセットへの期待 げっ歯類は生命科学分野の理解と発展に大きな貢献をしてきたが、系統学的な距離により、得られた結果を直接ヒトに外挿できない事もある。よりヒトに系統学的に近い霊長類コモンマーモセットは小型で繁殖効率が高く、実験動物としてのコロニーが存在するため、性別、年齢、体重などをコントロール群と実験群で複数匹揃えて実験を行う事ができる。また、多様な音声コミュニケーションを行い、オスが育児に参加し、模倣により新規行動を獲得するなど、ヒトに特徴的と言われてきたいくつかの行動認知機能を有している。さらに、遺伝子導入マーモセットの作出成功により今後、遺伝性疾患、脳高次機能疾患、霊長類の認知進化の生物学的基盤の解明など多様な研究分野でのマーモセットの有用性が期待されている。当センターでは2007年7月に4ぺアで飼育をはじめ現在80頭ほど飼育しており、3年後には300頭ほどを飼育し脳科学研究に活用される予定である。本講演ではマーモセットの飼育管理からその一般的特徴を紹介する。 (2)脳科学総合研究センター新実験動物飼育行動解析棟の紹介 脳科学研究に動物実験は必須であるが、既存の動物実験施設が手狭になったこと、より近代化した施設を必要とすることから、新しい動物実験施設を2011年3月完成予定で建設中である。新施設はマウス約20,000ケージ、ラット約3,000ケージの収容できる飼育室に加え、胚操作室、行動実験室、電気生理実験室、さらには見晴らしの良い飼育スタッフ用居室等を備える。飼育室と行動実験室は米国で盛んに取り入れられているスイート様式とし、飼育器材は個別給排気システムとし、省力化を目指して自動床敷供給廃棄及びケージ洗浄システム、ケージ台車自動運行システム、消毒用薬液生成及び供給噴霧システムなどを取り入れる。本講演では新施設の概要を紹介する。 |
| 第61回 | |
| 講師の都合により中止 | |